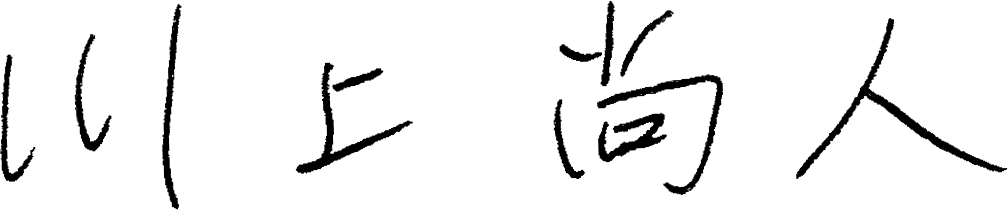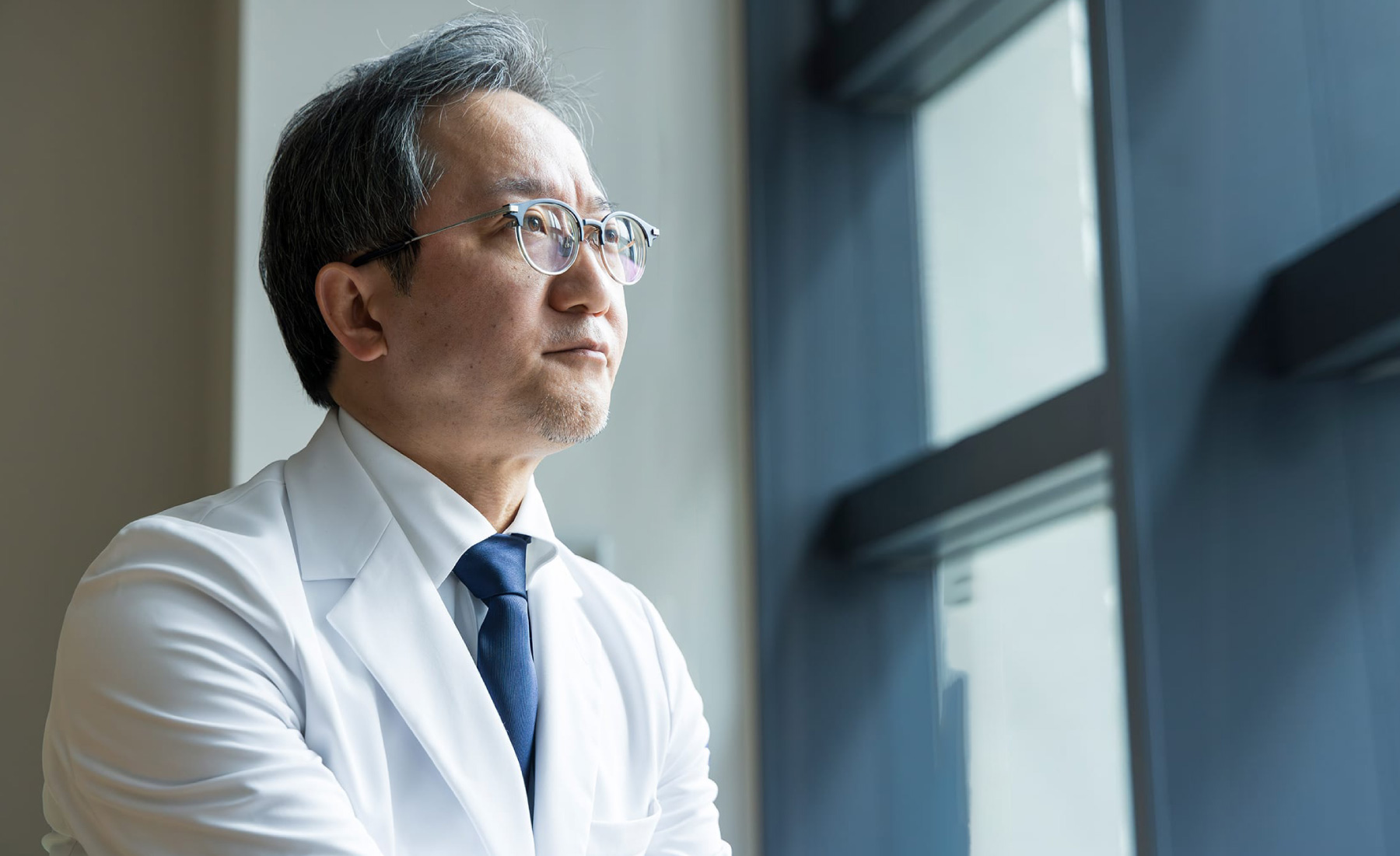
教授ごあいさつ
このたび東北大学大学院医学系研究科臨床腫瘍学分野および東北大学病院腫瘍内科の教授を拝命いたしました。本教室は1969年に初代教授である斉藤達雄先生の指導のもと、東北大学抗酸菌病研究所の臨床癌化学療法部門として設立されました。その後、涌井昭先生、金丸龍之介先生、石岡千加史先生と続く教授陣により、長年にわたり日本の臨床腫瘍学を牽引してきました。研究分野としては1993年、抗酸菌病研究所が加齢医学研究所に改組されたことに伴い、「腫瘍制御研究部門癌化学療法研究分野」と改名され、2010年にはさらに「臨床腫瘍学分野」となりました。2020年には、医学系研究科・医学部に「臨床腫瘍学分野」が新設され、診療科としても1975年に抗酸菌病研究所附属病院「化学療法科」として発足し、2000年には「腫瘍内科」へと改称されました。この歴史と伝統のある教室を引き継ぐにあたり、重責を痛感するとともに、身の引き締まる思いです。
がんになっても
不安のない社会を実現すること
私たちの目的は、「がんになっても不安のない社会」を実現することです。そのために、すべてのがん患者さんが希望を持ち続けられる医療を提供し、新たな治療選択肢を創出し続けることが求められています。特に、東北地方は広大で自然豊かな地域であり、地理的な制約から医療体制の充実には工夫が必要です。私たちは、この地域に住むすべてのがん患者さんが、最新の標準治療に迅速にアクセスできるような持続可能な医療システムの構築を目指します。そのためには、単に医療技術を導入するだけでなく、情報格差の解消、医療従事者の教育、地域医療ネットワークの強化が不可欠です。地方の腫瘍内科の発展こそが、日本のがん医療の未来を切り開くカギであると確信しています。
Bedside から Bench へ、
Bench から Bedside へ
Clinical Question から
Practice Changing へ
この目標を達成するために、私たちは「BedsideからBenchへ、BenchからBedsideへ」という理念のもと、臨床と研究の双方向的な発展を推進します。日々の診療の中で生じる疑問を研究へと昇華し、その成果を再び臨床へと還元することで、がん医療の革新を加速させます。最新のがん薬物療法を実践し、エビデンスの創出に貢献するとともに、国内外の研究機関と連携し、新規治療の開 発を推進します。また、地域の中核病院との協力体制を強化し、がん治療の均てん化を図るとともに、次世代の腫瘍内科医を育成し、研究と臨床を両立できる人材を輩出することにも力を注いでいきます。
そして 「Clinical Questionから
Practice Changingへ」
― 日々の診療から生まれる疑問を研究に昇華し、臨床現場へと還元する。この循環を絶え間なく回し続けることこそ 、私たちの使命です。
目指すのは、「世界をリードする腫瘍内科でありながら、地域のがん患者のために献身的な医療を提供する組織」です。世界水準の研究と教育を実践し、国際的な競争力を持つ腫瘍内科へと発展させるとともに、地域の患者さんが安心して治療を受けられる環境を整え、医療アクセスの格差を解消していきます。そして、新たな治療法を開発するだけでなく、患者さんにとって真に価値のある医療を届けることを目標としています。
こうした目標を実現するために、私たちは
「研究と診療の融合」
「患者中心の医療」
「チーム医療と多職種連携」
「グローバル視点」
「探求と革新」
「人材育成と継承」
という価値観を大切にし、医局全体でこれを実践していきます。特に、次世代の腫瘍内科医の育成には力を入れており、屋根瓦型の指導体制を整え、若手医師が研究と臨床の両面で成長できる環境を提供します。

未来の腫瘍内科を担う
若手医師の皆さんへ
このような理念に共感し、がん治療の未来を共に切り開いていきたいという若手医師の皆さんを、私たちは心から歓迎します。
「がん治療における
革新を生み出したい」
「世界に通用する
臨床研究を実践したい」
「地域医療の発展に貢献したい」
― こうした熱意を持つ方々とともに、私たちは研究と診療の両輪を回し、よりよい医療を実現していきたいと考えています。
私自身、まだまだ学ぶことの多い立場ですが、医局の仲間たちと共に学び、共に成長し、共にがん医療の未来を切り開いていきたいと考えています。新しいがん医療の未来を創るために、皆さんの積極的な参加をお待ちしております。
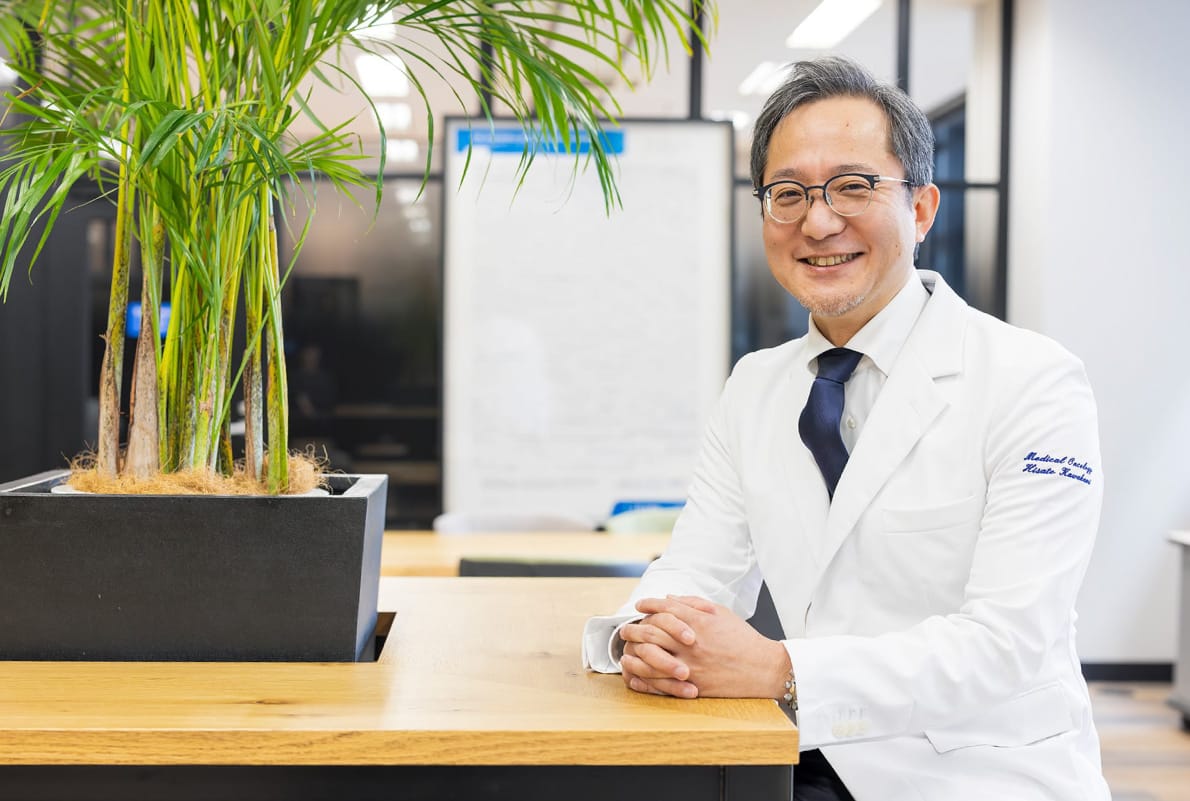
東北大学大学院医学系研究科
臨床腫瘍学分野
東北大学病院腫瘍内科